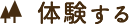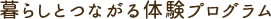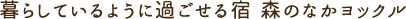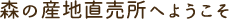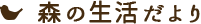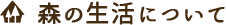北海道大学農学部森林科学科の同窓会「シルバ会」の会誌「シルバ85号」に代表の麻生が寄稿させていただきました。
同会の許可を得て、掲載させていただきます。
2010年に下川に移住してからのことを振り返りつつ書かせていただいた散文です。
下川という地域のひとつの見方、関わり方として、ご覧いただければ幸いです。(あそう)
北海道北部の田舎町 下川での9年間に想う これまで、今、これから
諸君よ 紺色の地平線が膨らみ高まるときに
諸君はその中に没することを欲するか
じつに諸君はその地平線に於る
あらゆる形の山岳でなければならぬ
(中略)
諸君はこの時代に強ひられ率ゐられて
奴隷のやうに忍従することを欲するか
むしろ諸君よ 更にあらたな正しい時代をつくれ
宇宙は絶えずわれらに依って変化する
潮汐や風、
あらゆる自然の力を用ゐ尽すことから一足進んで
諸君は新たな自然を形成するのに努めねばならぬ
(宮沢賢治「生徒諸君に寄せる」より)
故郷の名古屋から札幌に引っ越し、北大に入学した2003年の春、教養科目の哲学科の先生が講義の最中に詠った宮沢賢治の詩の一節である。この詩は、北海道下川町に暮らす今でも、読むたびに清々しいエネルギーをもらうことのできる、とても大切にしている文章のひとつだ。宮沢賢治は東北の田舎町で日々土に触れ、風を感じ、人々に混じりながら、子どものような心でまっすぐに未来を見つめていたんだろうと僕は想像する。土に根ざしながら、遠い宇宙に思いを馳せるその感性に、学生時代の僕は強い憧れを抱いたのだった。そんな心が、一時の都会でのサラリーマン生活を経て、僕を田舎へと運んだのだと思う。
北大森林科学科時代、実習や調査、そして旅を通じて出会った北海道の雄大で野性的な自然は、名古屋で生まれ育った僕に強烈なインパクトを与えた。そして、そんな野性的な自然のすぐ隣に人が暮らしている農山村地域を、とても魅力的に感じたのだった。学生時代に通った田舎町では、子どももお年寄りも、人と人の距離がとても近かった。食糧を畑や山から調達することができ、エネルギーを薪から得ることもできた。木材も身近にある。そんな、身近な人と自然が結びついたコミュニティが根づく農山村に、僕はとても惹かれたのだった。下川に暮らす今、あのころ憧れを抱いていたコミュニティの一員になっている。それは、様々な成り行きの末にではあるが、自分にとっては自然なことなのだと思う。仕事帰りにヤマメを釣ったり山菜を採ったり、休みの日には猟にも行ける(新米ハンターである)。町では老若男女に固有名詞で呼び合える知人がいて、困ったときは助けてもらえ、逆に力になることもできる。そんな生活が、自分にはしっくりくる。このような地域がずっと残っていてほしいと思う。
しかし、農山村地域の多くが近い将来に消滅してしまうかもしれないと言われている。2040年には、現在の自治体の約半数にのぼる約900の自治体が消滅しかねないという予測もある。下川町の人口推計をみると、現在(2019年2月1日時点)3,299人の人口は2030年には約2,400人台へ、2045年には1,500人台にまで減少すると予測されている(国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口[2018年推計])。病院や学校など暮らしを支える施設の存続についても、近い将来に正面から取り組まなければならない問題になるだろう。国内のほとんどすべての農山村地域が、同じような状況を抱えている。
この大きな時代の流れで、宮沢賢治の言葉を借りれば、ただ「奴隷のやうに忍従する」のではなく、乗り越え、「さらにあらたな正しい時代」につないでいくことができないものだろうか。その可能性があるのならば、あきらめ悪くいたい。
僕が北海道北部の田舎町、下川町に移住したのは2010年のことだ。90%が森林に覆われる過疎地域だが、この町は、政府から「環境未来都市」に指定されるなど、地方創生業界(そんな業界があるのかどうかは置いておいて)ではちょっと知られた地域でもある。
そんな下川に移住してから、気がつけば9年の歳月が経とうとしている。ありがたいことに、下川に来てから、地域内外にたくさんの気持ちの良い人たちと知り合いができ、いろいろな仕事や活動を担うようになり、立場としても、NPO法人の代表、木材加工工場での管理・営業の業務、町の委員など様々な面で地域に関わっている。その中での七転八倒が、先の「さらにあらたな正しい時代」をつくる動きをつくりだすことに少しでもつながっていれば、これほど嬉しいことはない。
そして現に、本当に幸せなことに、そういう未来につながっていると感じる瞬間が、この地域にいるとたびたびあるのだ。
下川町は、かつては鉱山の町として盛え、ピーク時には15,000人を超える人口を有したが、閉山後は記録的な急転直下の人口減少を記録。1956年には財政再建団体になるなど波乱の歴史を持つ。しかしながら、「伐ったら植える」60年サイクルの循環型森林経営や、森林資源を建築用材だけでなく、集成材、炭、割り箸、エッセンシャルオイルなど様々な製品へと木を無駄なく使い切るカスケード型の「ゼロエミッション」の林産業を目指し、地域ぐるみで林業の六次産業化を進めてきた。近年では木質バイオマスエネルギーによる地域熱供給にも取り組んでおり、公共施設の約60%の熱エネルギー(給湯、暖房)が、木質バイオマスによって賄われている。
今でこそ「森林未来都市」と冠をつけて地域づくりに取り組んでいる下川町だが、まだそのようなビジョンの無かったころ、官民混成で研究会を発足させ、連日連夜、まちの未来の姿について語り合った時期があったそうだ。1998年に発足した下川産業クラスター研究会におけるワーキンググループでの議論の末に描かれた「森林共生社会」は、今改めて眺めてみると、その主旨において多くのことが実現していることに気付く。そのような先人の構想力と、チャレンジの結果、今がある。
そして昨年、2018年には、2030年に向けた町のビジョンとなる「2030年の下川町のありたい姿」を官民で話し合う機会があり、僕も委員として関わらせていただいた。書籍「不都合な真実」の翻訳者でもある(有)イーズ代表の枝廣 淳子氏のサポートのもと、行政職員と住民委員による混成チーム20人を中心に、半年間で13回の議論を重ね、「しもかわチャレンジ2030」として下記の7つの目標を策定した。今後、このビジョンをもとに、総合計画の策定や各種施策を実施していくこととなっている。
1.みんなで挑戦しつづけるまち
危機や困難に挑戦し続ける不屈の精神や多様な人々、価値観を受け入れる包容力、寛容性などの「下川らしさ」を体現するまち
2.誰ひとり取り残されないまち
すべての人が可能性を拡げ続けられ、居場所と出番があり、健やかに生きがいを感じて暮らせるまち
3.人も資源もお金も循環・持続するまち
人・自然資源(森林・水など)・お金などすべての永続的な循環・持続、農林業など産業のさらなる成長、食料、木材、エネルギーなどの地消地産により、自立・自律するまち
4.みんなで思いやれる家族のようなまち
人とのつながりを大切に育み、お互いを思いやり、支え合って、安全で安心して住み続けられるまち
5.引き継がれた文化や資源を尊重し、新しい価値を生みだすまち
古くても大切なものは守り、新しい価値を生み出す「温故起新」のまち
6.世界から目標とされるまち
下川町のこれまでの取り組みを基盤に、さらに進化・深化させ、脱炭素社会の実現(パリ協定)や世界の持続可能な開発(SDGs)の実現に寄与するまち
7.子どもたちの笑顔と未来世代の幸せを育むまち
子どもたちがいきいき伸び伸びと成長するよう、すべての未来世代のことを考え、地域全体で育むまち
この目標の策定に至るプロセスの大きな特徴の1つは、SDGs(持続可能な開発目標)を踏まえて作成したことである。SDGsとは、国連で採択された、地球上で「誰ひとり取り残さない」ために2030年までに達成を誓った17つの目標のことである。SDGsは、経済と環境に加え社会的な課題も含めて、これらを統合的に解決していかざるを得ない時代に差し掛かっているというメッセージでもある。日本の場合、人口減少と高齢化(さらに言えば、後期高齢者の急増)というこれまで直面しなかった前提条件の中で取り組まなければならない。
下川町の高齢者率は39%であり、これは全国平均の約40年先を行く数字だ。つまり、時代の最先端である。したがって地方は課題「解決」先進地でなければならない。だから、課題解決の方法は、上記のように個別対策ではなく、できるだけ統合的に解決していく視点をもったものでなくてはならないだろう。石油由来のエネルギーから木質資源由来のエネルギーに切り替えることで、環境的には化石燃料由来の炭素排出量を削減し、経済的には地域外への資金流出を減らして地域内にお金の循環をつくり出すことで雇用を生み出す。結果的に、石油価格の変動に対して左右されにくい、しなやかなエネルギーインフラをもった地域社会づくりにもつながる…といったように。もちろん課題はある。しかし、失敗を恐れずにチャレンジしていく姿勢こそ、最も大切なものであろう。
僕が代表を務めているNPO法人森の生活でも、さまざまなチャレンジをしてきた。例えば、指定管理者として管理運営を行っている美桑が丘の森は、市民主体の森の場づくりに取り組んできた。2012年に森の生活が指定管理者になったころは、厚いクマザサに覆われ、枯損木だらけで、森に入ることもままならない状況だった。この場所をみんなが集える場所にしようと、住民の人たちとワークショップを何回も重ね、実際に体を動かしているうちに、美桑が丘で自由に過ごす月に1度の「みくわの日」や、どさんこ馬の放牧による植生回復の実験など、今では住民グループが運営を担う活動が数多く生まれている。夢のように語っていたことの多くが現実のものとなったのだ。昨年はバイオトイレを小屋づくりから行い、循環を体感できる場として、いっそうユニークな場になった(蛇足だが、自分の卒業論文のテーマが、そういえば市民参加の森林公園整備だったことを、最近になって思い出した)。また、毎年7月に開催される住民有志で開催する森のイベント「森ジャム」(2019年は7月6-7日開催予定)の会場になったり、名寄市立大学社会保育学科の実習の場としても利用されたりするようになった。
広葉樹の活用もチャレンジのひとつだ。国産広葉樹の約8割がチップにされているが、この中には木工等に活用できる原木も少なからず混ざっている。木工の材料として下川産の広葉樹を調達しようとした際に思いのほかその調達が難しく、その理由を探って山の現場に伺って作業員の方にお話を聞き、下川にもこのような状況があるということを知った。この広葉樹を活用できないかと、町内の森林組合や造材業者と連携して、パルプ材と銘木の中間の品質として木工用材として使用できる原木の仕分けを行い、地元の製材業者で製材、自社で低温乾燥機を導入して、2015年から「顔の見える木材」の産地直売機能を担うべく、下川産のナラ、タモ、シラカバ、ハン、ニレ、センなど、原木換算で年間約30㎥程度の少量多品種の広葉樹製材の流通の仕組みをつくりあげることができた。現在ではwebサイトを通じて、「しもかわ広葉樹」のオーダーメイド天板の販売も行っている。
このような地域ぐるみで森や木材を生かす取り組みに共鳴し、木工作家数名が下川に移住する現象も生まれた。木工作家のひとり「森のキツネ」の河野さんは、「家具乃診療所」を今年オープン予定である。これは、現在使われてない、かつて(人間向けの)診療所だった建物を改装して、家具の修理やオーダー家具の製作を行う拠点をつくる取り組みである。また、「クラフト蒼」の臼田さんは乾燥材を使ったクラフトだけでなく、生木を使った器の制作者だ。通常はチップにされてしまうような欠点のある木材も、彼の手にかかるとかけがえのない木の個性として転化され、味わいのある作品となる。東京で個展を開いたり、海外にも販路を持っていたりして、最近は全国雑誌にも取り上げられた。僕自身も、2017年からは下川の木材加工工場「下川フォレストファミリー(株)」の家具・クラフト部門の企画・営業の業務も担っており、札幌や東京圏で広葉樹を中心とした製品を販売する事業を広められるようにもなってきた。
他にも、森の生活を退職後、下川に残り、薪屋を立ち上げた者や、ゲストハウス運営兼バックカントリースキーガイド業を立ち上げた者もいる。どちらも、20代からこのようなチャレンジを始めた。
このような流れもあり、2017年からは、しもかわベアーズと呼ばれる起業家の誘致・支援プログラムの立ち上げと運営にも関わっている。「地域おこし協力隊」制度を活用して、給与と活動費が保証される3年間のうちに起業することをミッションに、自分のやりたい事業のプランを提案してもらい、選考と採用を行う仕組みで、今年も募集を行っている。このプログラムをきっかけにして、名古屋から移住してエゾ鹿肉関連ビジネスの起業を志す方や、札幌から移住してDIYのサポートを行うビジネスの起業に取り組む方も現れた。また、最近の傾向として、起業だけでなく、既存の企業や団体に就職し、余暇に小さなまちならではの活動に取組んでいる人も増えてきた。小さな映画会を企画したり、仲間と畑をしたり、釣りをしたり、サイクリングをしたり…というように、自分なりの「ちょうどよい」仕事と暮らしのスタイルを見つけて、仲間とともに自分らしく過ごす、そんな人たちも増えてきた。
僕も含め、これまでの登場人物に共通するのは、昭和につくられ平成の時代に維持されてきたような、これまでのステレオタイプな人生観から抜け出し、自分らしい人生、自分にとって自然体な人生を問い、実践を通じて模索していることにあるように思う。その結果として、「結果的に個性的」になった人たちから、地域の新しい可能性が次々と生まれているのだ。これは、とても嬉しい現象である。冒頭の詩にある「あらゆる自然の力を用ゐ尽すことから一足進んで」、「新たな自然を形成するのに努めねばならぬ」という一節の意味するところの、まさにその胎動を僕は感じるのである。「宇宙は絶えずわれらに依って変化する」のだ。
これまで紹介したような(僕も含めた)人たちのことを、昨年下川に移住した20代の物書きの子が「ネオ・ヒッピー」と呼んでいて、言い得て妙だなと思った。「自然」とか「共同体」といったようなヒッピー的な志向をどこか持ちながら、従来のヒッピーの持つ体制への否定や脱社会的な連帯感はそこにはない。地域コミュニティや地域の自然に根ざしながら、自分自身のやりたいことをオープンに共有し、仲間や、時にお金など資源を集めて実現させていく、そんな人たちである。地元の人も移住者も地域外の人も混ざり合いながら、ひとりひとりがある程度自立していて、でも必要な時には協力し合う。コンパクトだが、大きな広がりを持ったコミュニティである。
このような、ネオ・ヒッピーと名付けたくなるような潮流のなかに、閉塞した状況に見える今を乗り越えていく未来が秘められている気がしてならない。その先には、一人ひとりが自分にとって自然体の人生を歩む覚悟を持つがゆえに、地域の自然や社会とも調和した経済活動(金銭だけでなく、暮らしに必要なやりとりという意味での)を行っている、人も自然も心地よく調和した社会が透けて見える。地に足をつけて資本主義ともうまく付き合いながら、過度にストイックになるわけでもなく、でも適度に足るを知り、物心両面で充足している多様な人々によって結ばれたコミュニティ。決して閉鎖的ではなく、関わりしろのある余白と、身を置きたくなる居場所がいくつもある地域である。そんなネオ・ヒッピーの生態系が豊かになるにつれて、結果的にローカルから可能性が引き出され続けていく。
冒頭の一連の詩の中で、宮沢賢治はこうも語る。いつもこんな「風」を感じられる感性を守り育てたいものだ。
諸君はこの颯爽たる
諸君の未来圏から吹いてくる
透明な清潔な風を感じないのか
道北の地の気候風土は厳しい。この気候風土が作り上げた美しい自然の造形と、その中から地域をつくりあげてきた先人たちには畏敬の念を抱かずにはいられない。私たちは、過去を両手で受け止め、新たな風土を築いてゆく時代に生きているのだと思う。1日1日を、体いっぱい、人と自然とともに大切に生きようと、改めて思う。

麻生 翼 (あそう つばさ)
愛知県名古屋市出身。大学時代に訪れた北海道の農山村に魅せられ、気づけば下川に流れ着いていました。下川は個性豊かな人々が多くとても面白い町です。のんびり田舎暮らしはどこへやら…な日々ですが、たまの休日は山菜採ったり渓流釣りしたり、ときどき狩猟したり、森の生活を満喫しています。代表です。